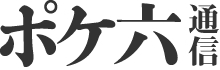●民事執行法の一部改正(令和5・6・14法53)
1.事件記録の電子データ化・閲覧に係る規定の整備
(1)執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものこととした。(17条の2関係)
(2)執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとした。(17条の3関係)
2.判決の電子化対応に係る仕組み等の整備
(1)民事執行の手続において民事執行法の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に裁判等に係る記録事項証明書を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該裁判等に係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができるものとした。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したとみなすものとした。(18条の2関係)
(2)そのほか、強制執行の実施(25条関係)、執行文の付与(26条2項関係)、債務名義等の送達(29条関係)等も所要の規定の整備をした。
3.オンライン提出等に係る規定の整備
民事執行の手続における申立て等のうち、当該申立て等に関する民事執行法その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができることとした。(19条の2関係)
4.期日におけるウェブ会議等の活用
執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに民事執行法85条1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、配当期日における手続を行うことができるものとされた。その配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなすものとした。(86条関係)
執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、財産開示期日における手続を行うことができるものとすること。その財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなすものとした。(199条の2関係)
また、映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述(199条の3関係)も所要の規定の整備をした。
5.登記事項証明書の提出の省略を可能とする規定の整備
不動産担保権の実行は、担保権の登記(仮登記を除く)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立の申立て又は登記事項証明書の提出があったときに限り、開始するものとした。(181条関係)
その他、不動産の売却不許可事由について意見を陳述すべき期間の指定(70条関係)、電子配当表に記録された各債権者の債権又は配当の額に対する異議申出期間の指定(85条の2関係)など所要の規定の整備をした。
この改正は令和10年6月13日までに施行される。
ただし、①上記2(2)及び5に係る規定の改正については令和7年10月1日(令和7・7・18政262)に施行され、②上記2(1)及び4に係る規定の改正については令和8年5月17日までに施行される。