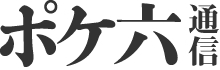◎民法の一部改正(令和4・12・16法102)
…女性の再婚禁止期間を撤廃し,子どもの無戸籍問題の解消のため,妊娠や出産の時期により父親を推定する「嫡出推定」制度を見直すとともに,離婚後300日以内に生まれた子であっても,女性が出産時までに再婚していれば現夫の子とする改正。
1 再婚禁止期間の撤廃等
再婚禁止期間に関する規定を削除し,所要の見直しを行うこととした。(733条,746条及び773条関係)
2 嫡出の推定
(1) 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定することとし,女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とすることとした。(772条1項関係)
(2) (1)の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定することとした。(772条3項関係)
3 嫡出の否認
(1) 父,子又は母は,子が嫡出であることを否認することができることとした。(774条1項及び同条3項関係)
(2) 子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって,子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は,子が嫡出であることを否認することができることとした。(774条4項関係)
4 嫡出否認の訴え
父,子,母及び前夫の否認権は,それぞれ所定の者に対する嫡出否認の訴えによって行うこととした。(775条1項関係)
5 嫡出否認の訴えの出訴期間
(1) 父,子,母及び前夫の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは,それぞれ所定の時期から3年以内に提起しなければならないこととした。(777条関係)
(2) 子は,その父と継続して同居した期間が3年を下回るときは,21歳に達するまでの間,嫡出否認の訴えを提起することができることとした。(778条の2第2項関係)
6 認知の無効の訴え
(1) 子若しくはその法定代理人,認知をした者又は子の母は,それぞれ所定の時期から7年以内に限り,認知について反対の事実があることを理由として,認知の無効の訴えを提起することができることとした。(786条1項関係)
(2) 子は,その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間が3年を下回るときは,21歳に達するまでの間,認知の無効の訴えを提起することができることとした。(786条2項関係)
7 子の人格の尊重等
親権を行う者は,監護及び教育をするに当たっては,子の人格を尊重するとともに,その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず,かつ,体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととするとともに,懲戒に関する規定を削除することとした。(821条及び822条関係)
この改正は,令和6年4月1日(令和5・4・26政173)に施行される。なお,7の改正は令和4年12月16日から施行される。
*この改正に伴い,国籍法,児童福祉法,児童虐待の防止等に関する法律,人事訴訟法,家事事件手続法等も改正された。